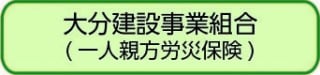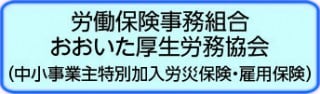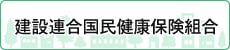世帯全体の高額療養費
高額療養費
被保険者が同じ月内に一つの病院、診療所で支払った保険医療の一部負担金が所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請により、後日支給されます。
なお、自己負担限度額は世帯に属する(保険証に記載されている)すべての方の所得の合計により、上位所得世帯1・2 / 一般 1・2/ 低所得世帯の5つに区分されています。
なお、自己負担限度額は世帯に属する(保険証に記載されている)すべての方の所得の合計により、上位所得世帯1・2 / 一般 1・2/ 低所得世帯の5つに区分されています。
所得区分
区分
| 世帯に属するすべての方のの基礎控除後の総所得金額の合計額
|
上位所得1
| 901万1円以上(年収約1,160万円以上)
|
上位所得2
| 600万1円~901万円(年収約770~約1,160万円)
|
一般1
| 210万1円~600万円(年収約370~約770万円)
|
一般2
| 210万円以下(年収約370万円未満)
|
低所得
| 市町村民税が課されていない(非課税)世帯
|
※療養のあった月の属する年の前年(療養のあった月が1月から7月までの場合は前々年)の所得によって判定されます
※世帯に属するすべての方とは、建設連合国民健康保険組合にご加入されている方全員を指します。
自己負担限度額
上位所得1
| 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
|
上位所得2
| 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
|
一般1
| 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
|
一般2
| 57,600円
|
低所得
| 35,400円
|
世帯合算
同じ世帯で同じ月に2万1千円(70歳以上74歳以下の高齢者の合算は1円)以上の一部負担金が複数生じたとき、これを合算して所得に応じた自己負担限度額を超えた額が支給されます。
2万1千円以上 + 2万1千円以上
多数該当
同じ世帯で1年間(診療を受けた月以前12か月)に既に3回高額療養費の支給を受けた場合(限度額認定証を使用したときも含む)は、4回目からは多数該当として次の額を超えた額が支給されます。
上位所得1
| 140,100円
|
上位所得2
| 93,000円
|
一般1
| 44,400円
|
一般2
| 44,400円
|
低所得
| 24,600円
|
≪申請に必要なもの≫
●高額療養費支給申請書【←クリックするとダウンロード可能です。】
●高額療養費支給申請書【←クリックするとダウンロード可能です。】
●マイナンバーについての書類等(詳細はこちら!)
●医療機関の領収書のコピー
●保険証
●印鑑
●一般区分該当世帯は、その世帯(保険証に記載されている)の被保険者全員の所得証明書
※場合によっては所得証明書の他に市区町村長発行の住民税納税通知書の総所得金額が記載された部分のコピーを求めることがあります。
※低所得世帯は、その世帯(保険証に記載されている)の被保険者全員について市区町村長発行の非課税証明書を添付してください。
※その世帯(保険証に記載されている)にハローワークから特定受給資格者及び特定理由離職者として雇用保険受給資格証を交付されている被保険者がいるときには、そのコピーを添付してください。所得を軽減して所得区分を判定する場合があります。
※けがの場合は、負傷原因報告書の提出をお願いします。
※所得証明書または非課税証明書の提出をされない場合には上位所得世帯として判定されます。
※70歳以上74歳以下の高齢者が合算対象の場合は前期高齢者高額療養費申請明細書(内訳)も提出してください。
●医療機関の領収書のコピー
●保険証
●印鑑
●一般区分該当世帯は、その世帯(保険証に記載されている)の被保険者全員の所得証明書
※場合によっては所得証明書の他に市区町村長発行の住民税納税通知書の総所得金額が記載された部分のコピーを求めることがあります。
※低所得世帯は、その世帯(保険証に記載されている)の被保険者全員について市区町村長発行の非課税証明書を添付してください。
※その世帯(保険証に記載されている)にハローワークから特定受給資格者及び特定理由離職者として雇用保険受給資格証を交付されている被保険者がいるときには、そのコピーを添付してください。所得を軽減して所得区分を判定する場合があります。
※けがの場合は、負傷原因報告書の提出をお願いします。
※所得証明書または非課税証明書の提出をされない場合には上位所得世帯として判定されます。
※70歳以上74歳以下の高齢者が合算対象の場合は前期高齢者高額療養費申請明細書(内訳)も提出してください。
 一部負担金の基準 一部負担金の基準◎同じ病院でも、入院と外来は別計算になります。 ◎同じ病院内でも、医科と歯科は別計算となります。 ※ただし、上記の場合、それぞれ2万1千円(70歳以上74歳以下の高齢者は1円)以上の一部負担金の場合には、世帯合算の対象となります。 ◎月の1日から末日までを1か月とします ◎退院後、同一月内に同じ病院へ再入院した場合はあわせて計算されます。 ◎保険診療外の差額ベット代などは、一部負担金には含まれません。 ◎入院時食事療養費の標準負担額は含まれません。 ◎病院の処方箋により保険薬局で支払った薬代は、病院分の一部負担金に合算することができます。 |
限度額適用認定申請(高額療養費の現物給付制度)
70歳未満の被保険者が、組合に申請し限度額認定証の交付を受け、医療機関等へ限度額認定証を提示することにより、一つの医療機関等ごとの窓口での支払いが自己負担限度額にとどまります。
現物給付の対象となるのは保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者で受けた保険診療です。(柔道整復・鍼灸・あん摩マッサージの施術はどは対象外です)
低所得世帯にて限度額認定証を交付された後90日以上入院された場合、上旬負担額減額認定の申請をすることにより食事代が減額になります。(ただし、低所得と判定された限度額認定証の交付を受けていることが前提です)
≪申請に必要なもの≫
●国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書【←クリックするとダウンロード可能です。】
●印鑑
●保険証
●低所得世帯で90日以上入院の場合、90日以上入院したことを証明するもの(医療機関発行の
医療費領収書もしくは請求書)
●一般区分該当世帯は、その世帯(保険証に記載されている)の被保険者全員について【所得証明書】の添付が必要となります。また場合によっては所得証明書の他に市区町村長発行の住民税納税通知書の総所得金額が記載された部分のコピーを求めることがあります。
●低所得世帯は、その世帯(保険証に記載されている)の被保険者全員について、市区町村長発行の非課税証明書を添付してください。
※所得証明書または非課税証明書の提出をされない場合には上位所得世帯として判定されます。
※保険料納入が確認できない時は、受け付けができない場合もあります。
特定疾病
治療が長期にわたり、自己負担が著しく高額になる以下の(1)〜(3)については1か月1万円を限度とする支払いですみ、1万円を超える部分は高額療養費として現物給付されます。
この給付を受けるためには、組合に「特定疾病認定申請書」(医師の証明が必要)を提出して、組合から「特定疾病療養受療証」の交付を受け、これと保険証を病院等の窓口に提出します。
(1)血友病
(2)人口透析治療を行う必要のある、慢性腎不全
(3)抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める人に限ります)
(2)について70歳未満の方は、上位所得世帯の場合、自己負担限度額が2万円となります。
 こちらの申請については本部事務局へ直接連絡していただくことになります。
こちらの申請については本部事務局へ直接連絡していただくことになります。
問い合わせ先 TEL:03−3504−1502
FAX:03−3504−1243
組合員専用フリーダイヤル 0120−76−1703
この給付を受けるためには、組合に「特定疾病認定申請書」(医師の証明が必要)を提出して、組合から「特定疾病療養受療証」の交付を受け、これと保険証を病院等の窓口に提出します。
(1)血友病
(2)人口透析治療を行う必要のある、慢性腎不全
(3)抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める人に限ります)
(2)について70歳未満の方は、上位所得世帯の場合、自己負担限度額が2万円となります。
 こちらの申請については本部事務局へ直接連絡していただくことになります。
こちらの申請については本部事務局へ直接連絡していただくことになります。問い合わせ先 TEL:03−3504−1502
FAX:03−3504−1243
組合員専用フリーダイヤル 0120−76−1703